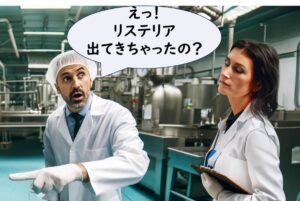■ 過去20年間の注目論文
過去20年間の世界での注目論文を解説します。これらの記事を読むことによって 食品微生物学の各トッピクス の基礎力が身につきます。このコーナーの記事は、次の記事によって構成されています。
1)公益社団法人日本食品衛生学会の会員限定メールマガジンで私が執筆した記事を、学会の許可を得て、メルマガ発行以後1年以上経ったものについて公開しています。ただし、最新状況を反映して、随時、加筆・修正しています。
2)本ブログのためにオリジナルに書き下ろした記事。
【最新ニュース】乳幼児用粉ミルクのセレウリド汚染:グローバル供給網に潜む「死角」を考察する新着!!
先週(2026年1月下旬)、世界の食品安全関係者の間で重大な関心を集めるニュースが飛び込んできました。フランスの乳業大手ダノン(Danone)社をはじめ、ネスレ、ラクタリスといった世界的企業が、乳幼児用粉ミルクの広範囲な自主回収を開始しました。原因は、セレウス菌が産生する耐熱性毒素「セレウリド(Cereulide)」による汚染の疑いです。フランスではすでに乳児の死亡事例も報告されており、当局による厳重な捜査が進められています。なぜ、高度な品質管理を誇るはずの乳業大手が、これほど大規模な汚染を許してしまったのか。その背景には、グローバルな原材料供給網の「盲点」がありました。
スペインの食品安全委員会が示した消費期限設定の科学的アプローチ:小売店でスライスされたRTE食品に焦点を当てて
食品の安全性を確保するうえで、消費期限の設定は極めて重要です。一般的に、食品メーカーが製造するパッケージ製品では、消費期限が厳密に設定されています。しかし、小売店舗のバックヤードでスライスされ、パッケージされたReady-to-Eat(RTE)食品については、その消費期限が曖昧である場合があります。このような背景を受け、スペイン・バルセロナ公衆衛生局は、小売店舗でスライス・パッケージされるRTE食品の安全な消費期限を科学的に評価し、明確な指針を策定する必要性を認識しました。この問題に対処するため、バルセロナ公衆衛生局は、スペイン国内の食品安全科学諮問委員会に調査を依頼しました。この委員会は、食品の安全性に関する科学的助言を行うスペインの専門機関で、EU基準に準じた評価手法を採用しています。その結果、リステリア菌の増殖リスクを科学的に評価し、消費期限を「5日未満」と設定する結論が導き出されました。本記事では、このプロセスを解説し、食品品質管理の現場で役立つ知見をお届けします。
リステリア菌の脅威:カット野菜・果物工場の汚染実態を徹底調査
前記事では、EUにおける乳製品および食肉製造工場におけるリステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)の汚染実態を環境モニタリング調査によって明らかにしました。それでは、カット野菜工場における汚染状況はどうでしょうか?実は、L. monocytogenesによる食中毒は最近、肉製品だけでなくカットフルーツ、カット野菜、ミックスサラダ、冷凍野菜などでも多発しています。このような実態を受け、これらの加工工場におけるL. monocytogenesの汚染状況を明らかにする必要があります。本記事では、カット野菜・果物・ミックスサラダ工場における汚染実態を探ります。
冷凍野菜のリステリア汚染リスク:英国で明らかになった実態
冷凍野菜は、消費者が購入後に加熱・調理することを前提に流通しているため、リステリア菌に関する基準はEUでも設定されておらず、Ready to Eat (RTE)食品とはみなされていません。しかし、リスクは消費者の誤解だけに留まりません。加工業者が誤って冷凍野菜を加熱せずに使用してしまうことも、食中毒の原因となります。実際、以前紹介したEUでの冷凍スイートコーンによるリステリア食中毒事件では、消費者が冷凍食品を生で食べたことに加え、加工業者の誤った処理も関与していました。本記事では、英国公衆衛生庁(Public Health England: PHE)の研究グループの調査結果をもとに、冷凍野菜のリステリア汚染実態調査の結果を紹介します。
EAEC(腸管凝集付着性大腸菌)による富山県ホテル食中毒 ― “ヒト”が宿主の大腸菌に注意
2025年10月11日に富山県のホテルで集団食中毒が発生した。原因となったのは、聞き慣れない 腸管凝集付着性大腸菌(EAEC) である。腸管出血性大腸菌(EHEC)はよく知られているが、EAECを知っている人は食品業界でも少ないだろう。特に「この菌はどこから来るのか」「何に気をつければいいのか」という点は、品質管理担当者にとって極めて重要な視点である。本稿では、この菌の特徴と感染源について、実務的な観点から整理する。
EUの乳製品および食肉製造工場のリステリア菌の環境モニタリングで、3つの汚染シナリオが判明
非加熱喫食食品、すなわち消費者が購入後そのまま食べるready-to-eat(RTE)食品の製造において、加工後の工場環境からのリステリアの二次汚染は致命的です。これらが流通過程で増殖することで、リステリア症に直結する可能性があります。そのため、RTE食品を製造する工場では、HACCPによる製造工程のCCPに加え、食品工場環境からの二次汚染防除のための環境モニタリングが重要な戦略となります。この記事では、EUの複数の国々の中小規模の食品製造工場において、リステリア菌がどの程度、どのような場所で検出されているかを示したレポートを紹介します。
卵は洗うべきか、冷やすべきか──日米欧に見る制度と微生物リスク管理法の違い
なぜ米国や日本の卵は冷蔵されているのに、EUでは常温で売られているのか?リスク管理や科学的根拠に基づいて国や地域ごとの制度の違いを比較してみると、卵の流通管理方法の国際的な違いは、洗浄の有無を含めて非常に示唆的で興味深い。本記事では、食品微生物の立場から、日米欧における卵の取り扱いの違いを、リスク管理と科学的理解の観点から整理し、各国の制度の背景と科学的根拠を比較する。
冷凍野菜に潜む危険: スイートコーンとリステリア事件
国際的にリステリア・モノサイトゲネスに関する厳格な規格基準が設定されているのは、消費者が加熱せずにそのまま食べる「Ready to Eat: RTE」食品に限定されています。例えば、冷凍野菜や生鮮野菜のように加熱調理を前提としている食品については、原則として規制の範囲外です。しかし、最近では韓国や中国から輸出されたエノキダケのように、本来は加熱・調理を目的とした食材でも、消費者が生で食べたために食中毒が発生する事例が見られ、これらの食材に対してカナダや米国で厳しい規制がかけられ始めています。この記事では、2015年から2018年にかけて欧州で発生した冷凍スイートコーンによるリステリアの大規模な食中毒事件の概要を紹介し、RTE食品ではない冷凍野菜におけるリステリアリスクの問題に焦点を当てます。
消費期限設定するために、消費者の冷蔵庫温度を何°Cと仮定すべきか?
欧州連合(EU)では、食品事業者が消費期限を科学的に設定する際、消費者の家庭用冷蔵庫の温度をどのように想定すべきかが大きな関心事となっています。これまで12℃が想定温度の目安とされていましたが、最近の広域調査により、実際の家庭環境を反映した温度として「10℃」が新たに推奨されるようになりました。今回紹介する研究では、欧州16カ国の冷蔵庫温度データを解析し、この「10℃」という数値が、より現実的で妥当な想定値であることが示されています。
※なお、この研究はリステリア菌のリスク評価を想定したShelf-life試験の文脈で実施されていますが、示された冷蔵庫温度データは消費期限設定全般にも応用可能な基礎情報となっています。
知らぬ間にリスクが潜む?固体表面に触れた手で顔に触る頻度を検証
ノロウイルスは手洗いを怠った感染者が触れた生活空間の固体表面から感染します。また、呼吸系の感染症は鼻粘膜に汚染された指との接触で広がります。日常生活の中で、私たちはどれほど頻繁に固体表面に触れた手で顔の粘膜に触れているのでしょうか?この記事では、これらの接触頻度について統計的に整理された論文を紹介します。