かつて食品微生物検査の主役の一つであった「大腸菌」や「大腸菌群」。だが今、EUの食品衛生管理の舞台では、以前ほどの頻繁な登場は見られない。食品安全基準という「本舞台」においては、大腸菌の役割は大きく縮小し、主な出演の場は特定の「特番枠」である二枚貝に限られている。また、工程衛生基準という「新しい番組」でも、大腸菌の出演機会は限定的である。一方、大腸菌群は制度全体から完全に姿を消した。本稿では、2005年にEUで施行された Regulation (EC) No 2073/2005 を出発点とするこの“配役交代”の背景にある制度と科学の視点を解説していく。
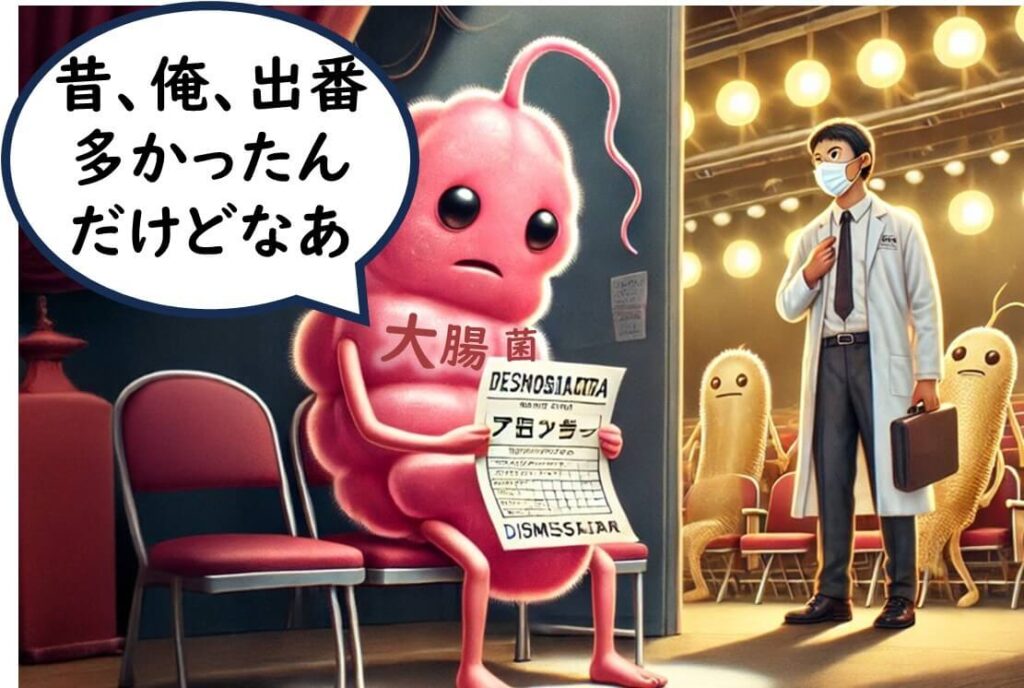
※本記事では、「俳優」「舞台」「キャスティング」などの表現を比喩的に用い、微生物が制度・現場で果たす役割の違いを視覚的に捉えやすくしています。各菌の科学的・制度的な位置づけは、それぞれのセクションで具体的に示しています。
俳優たちの再配役──指標菌達の「出番」が変わった
この大きな転換の出発点となったのは、2005年にEUで施行された Regulation (EC) No 2073/2005である。
食品衛生の法体系がHACCP制度に整合するよう再構築され、「病原菌の直接検出」を中心とする新たな基準が導入されたことで、それまで広く用いられていた“指標菌”たちの立場は大きく変わることとなった。
かつてEUでは、大腸菌(E. coli)は食品衛生の現場に欠かせない“常連俳優”であった。製品の汚染や衛生状態を間接的に示す“指標菌”として、各地の舞台でその姿を見せていた。
しかし、Regulation (EC) No 2073/2005 の施行により、EUがHACCP制度との整合を図るため、食品微生物基準を抜本的に見直したことで、舞台の主軸は「指標菌による推測」から「病原菌そのものの検出」へと大きく変わることとなった。
その結果、大腸菌を含む指標菌グループは原則として“降板”を告げられ、新たに登場した「工程衛生基準」という舞台へ、配役変更を迫られることになる。
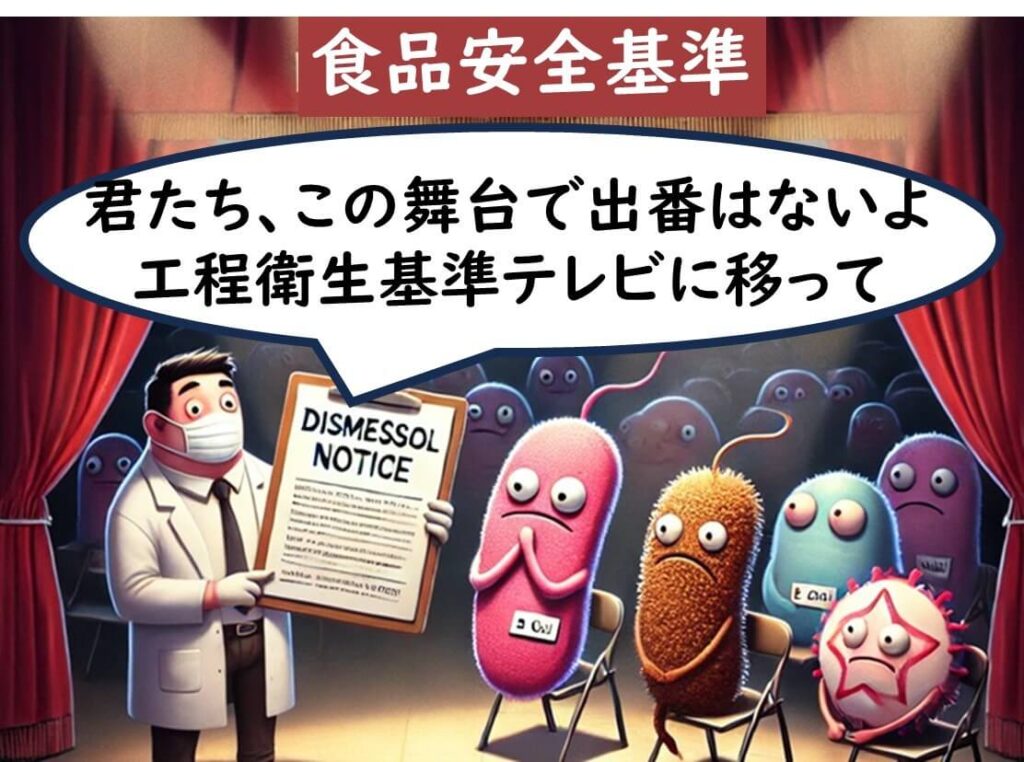
大腸菌群は完全引退──制度が切り捨てた「不明瞭な俳優」
この制度変更において、最も明確に“完全引退”を言い渡されたのが「大腸菌群(coliforms)」である。日本や米国の乳製品では今も食品の衛生指標として広く使われているが、EUではその科学的定義の曖昧さが問題視された。
大腸菌群とは、乳糖を分解してガスを発生させる好気性または通性嫌気性グラム陰性桿菌の集団であるが、そこには食中毒と無関係な菌も含まれている。EUはこの点に着目し、「曖昧な定義のまま制度に残すことは合理性を欠く」と判断。Reg. 2073/2005の中では一度もその名が登場せず、事実上、制度からの完全排除が実行された。
つまり、大腸菌群はEU制度という舞台においては「もう脚本にも名前が載っていない俳優」となったのである。

🏢 工程衛生基準テレビ ——「主役」は誰の手に?
こうして“食品安全基準”という本舞台を降板した指標菌グループは、新天地である「工程衛生基準テレビ」局のオーディションに向かう。
だが、そこに待っていたのは――さらなる“選別”であった。
プロデューサー(=EU衛生管理者)はこう判断した:
- E. coli(大腸菌)は環境ストレスにも弱く、加熱後製品では検出されにくい傾向がある
→タフな神経が要求される工程衛生テレビ向きではない。 - 腸内細菌科菌群は環境ストレスにも強く、設備の清掃や交差汚染の評価に向いている
→ “頼れる現場型俳優”として、連続ドラマ(定期モニタリング)のレギュラー出演が決定。

💥結果、大腸菌はこのテレビ番組ではレギュラー出演は少なく、仲間だったはずの腸内細菌科菌群だけが脚光を浴びる。腸内細菌科菌群は、食肉処理、乳・卵の加熱製品、アイスクリーム、粉ミルクなど、多様な食品カテゴリーにおいて、工程衛生の“頼れるレギュラー俳優”として定着している。

──ただし、大腸菌も完全に姿を消したわけではない。
工程衛生基準Annex I にも、特定の食品カテゴリーにおいては大腸菌の基準値が設定されており、大腸菌にはいくつかの「ピンポイント出演枠」が残されている。
例えば、非加熱食肉製品の現場(工程衛生基準Annex I: 1.1)では、「病原性大腸菌O157問題」が依然として深刻だ。ここでは、病原性大腸菌のリスクを示す重要な指標として、大腸菌の起用が今なお欠かせない。
一方、ナチュラルチーズ(低温殺菌された乳またはそれ以下の加熱処理乳から作られるもの、工程衛生基準Annex I: 1.2)や、未殺菌フルーツジュース(Annex I: 1.6)では、糞便汚染を示す指標として大腸菌が用いられている。
- ナチュラルチーズ
- 未殺菌フルーツジュース
いずれも、原料段階や製造初期における糞便由来の汚染リスクを監視する目的で、大腸菌が用いられている。
つまり、大腸菌は工程生成基準テレビの“レギュラードラマの主役”ではないかもしれないが、特番や社会派ドラマの「再現フィルム枠のいぶし銀俳優」として、必要な場面では出演枠が僅かに残されているのである。

本舞台への“細々カムバック”──大腸菌に残された最後の役どころ
こうして大腸菌は、“テレビ局”である工程衛生基準の世界ではレギュラーの座をつかめず、脚光を浴びることはなかった。
だが彼は、かつての本拠地──食品安全基準という“舞台”の扉を、もう一度叩いてみることにした。
舞台の責任者はしばし沈黙したあと、こうつぶやいた。
👴「うーん……基本的にもう指標菌グループは使ってないんだけどねぇ。
でも、君のキャリアは評価してるよ。飲料水と生食用二枚貝だけは、まだ君の力が必要なんだ。」
食品安全基準の主役はすでに病原菌の直接検出に移っていたが、特定のリスクが高い場面──飲料水の安全確保や生食用二枚貝の汚染防止などでは、糞便汚染の確実な指標としての大腸菌の起用が今も続いている。

✅ まとめ:新時代の配役交代──制度が選んだ菌たちの適材適所
2005年、Reg. (EC) No 2073/2005 の施行によって、EUの衛生基準は「科学的根拠に基づいた合理的な基準」へと大きく転換した。
以下は、現在のEU制度における三者の“キャスティング”の全体像である。
| 観点 | 大腸菌群(Coliforms) | 大腸菌(E. coli) | 腸内細菌科菌群(Enterobacteriaceae) |
|---|---|---|---|
| 役割 | 昔は加熱生残や衛生の指標 | 糞便汚染の指標 | 工程衛生の指標 |
| 制度での扱い | 制度から完全除外 | 限定的に使用 | 主な制度的指標として採用 |
| 強み | 歴史的に使われてきた | 糞便汚染を明確に示せる 腸管出血性大腸菌の指標 | 加熱後も残りやすく、使いやすい |
| 弱み | 定義が曖昧で科学的根拠が弱い | 環境に弱く、検出が難しいことも | 糞便指標にはならない |
| 立場(比喩) | 引退した旧俳優 | 元主役、今は特番(腸管出血性大腸菌、糞便汚染)ゲスト | 工程衛生の現場で活躍中のレギュラー俳優 |

