これまでの記事では、日本の食品微生物規格がHACCP導入後も昭和期の製品検査型の枠組みを引きずっていること、そしてEUではHACCPに連動したリスクベースの規格が確立されていることを紹介してきた。
制度の整備状況だけを見れば、日本は国際的に大きく遅れているように映る。

しかし、2023年の最新データをもとに実際の食中毒発生率を比較してみると、むしろ日本の方がEUよりも低いという興味深い結果となる。
本記事では、その背景にある構造的・制度的な違いを再確認しつつ、「制度の遅れ」と「統計上のリスク低さ」がなぜ同居しているのかを考察していく。
サルモネラ症、腸管出血性大腸菌感染症(STEC)、リステリア症を中心に、100万人あたりの発生率を比較し、補足としてカンピロバクター症のデータも取り上げる。
制度の優劣は、そのままリスクの大小に結びつくのか?――その答えを、データから読み解く。

日本とEUの食中毒発生率を比較する
本記事では、日本の厚生労働省とEUのEFSA(欧州食品安全機関)の2023年のデータを基に、サルモネラ症、腸管出血性大腸菌感染症(STEC)、リステリア症に限定して食中毒の発生率を比較する。また、食品微生物規格には含まれていないが、主要な食中毒原因菌であるカンピロバクターについても、参考としてデータを確認する。
100万人あたりの患者数という共通の指標を用いることで、日本の食品安全の実態を検証していく。
データの収集と統一方法
食中毒の発生状況を比較するにあたり、以下のデータを使用した。
- 日本のデータ:厚生労働省「食中毒統計(2023年)」
- EUのデータ:EFSA「One Health 2023 Zoonoses Report」
両者のデータは統計手法が異なるため、比較にあたって考慮すべき違いがある。
1. 集計範囲の違い
- 日本のデータ:「報告された食中毒患者数」に基づいており、医療機関を受診した患者を中心に集計
- EUのデータ:「感染症サーベイランス」に基づき、入院患者データが中心。そのため、実際の感染者数は報告値より多い可能性がある。
📌 注意点:
EUのデータは、特に症状が重く入院を要するケースが多く含まれているため、実際の感染者数は過小評価されている可能性がある。
一方、日本のデータは入院を伴わない比較的軽症例も報告される傾向があるため、統計方法の違いを考慮した解釈が必要。
2. 人口規模の違い
- 日本の人口:約1億2,500万人
- EU全体の人口:約4億8,000万人
この違いを調整するため、100万人あたりの患者数 を算出し、日本とEUを統一的な指標で比較できるようにした。
実際の食中毒発生率は? 日本 vs. EU
では、実際のデータをもとに、日本とEUの食中毒発生率を比較してみよう。
日本とEUの食品微生物規格基準の違いは、特にサルモネラ、腸管出血性大腸菌(STEC)、リステリアの規制の有無やサンプリングプランの違いに顕著に現れる。そこで、本記事ではこれら3つの食中毒菌に限定し、食中毒発生率を比較することで、微生物規格基準の違いが実際の発生率にどのような影響を与えているのかを考察する。また、カンピロバクター症についても、食品微生物規格には含まれていないものの、主要な食中毒原因菌であるため参考データとして確認する。
EUでは、これらの病原菌について厳格なサンプリングプランに基づいた微生物規格が食品安全基準として設定されており、明確な基準に基づく管理が行われている。一方、日本ではサルモネラについてもn=1の基準が採用されており、全体として規格基準は緩やかである。また、日本では指標菌が食品安全基準に含まれている点も、EUとは大きく異なる特徴の一つである。
こうした違いが実際の食中毒発生率にどのような影響を与えているのか?日本の基準の緩さが、食中毒のリスクを高めているのか? それとも、実態は異なるのか?
次のデータを基に、日本とEUの発生率を比較していく。
日本とEUの病原菌別食中毒比較表(2023年)
| 病原菌 | 日本_患者数 | 日本_死者数 | EU_患者数 | EU_死者数 |
|---|---|---|---|---|
| サルモネラ症 | 655 | 1 | 77,486 | 88 |
| 腸管出血性大腸菌 | 265 | 1 | 10,217 | 31 |
| リステリア症 | 0 | 0 | 2,952 | 335 |
| カンピロバクター症 | 2,089 | 0 | 148,181 | 44 |
この表のデータを見ると、EUのほうが全体的に患者数が多い。特にサルモネラ症の患者数は、日本と比べて大きな差がある。
しかし、日本とEUでは 人口規模が異なる ため、単純な患者数の比較ではなく、100万人あたりの患者数 で統一して発生率を算出する必要がある。
そこで、日本とEUの食中毒発生率を 「100万人あたりの患者数」 で統一し、より正確な比較を行う。
📌 計算方法
100万人あたりの発生率は、次のデータを元に算出する。
- 日本の総人口: 約1億2,500万人
- EUの総人口: 約4億8,000万人
この計算に基づき、次の表に 100万人あたりの発生率 を示す。
日本とEUの100万人あたりの患者数と比率(2023年)
| 病因物質 | 日本_100万人あたり患者数 | EU_100万人あたり患者数 | 比率(EU/日本) |
|---|---|---|---|
| サルモネラ症 | 5.2 | 161.4 | 31.0 |
| 腸管出血性大腸菌 | 2.1 | 21.3 | 10.1 |
| リステリア症 | 0.0 | 6.2 | ∞(※) |
| カンピロバクター症 | 16.7 | 308.7 | 18.5 |
この表のデータを見ると、EUのほうが100万人あたりの患者数も10倍以上、最大で30倍以上と多い
✅ まとめ:データが示す日本とEUの食中毒リスクの違い
- サルモネラ症の発生率
- EUは日本の約30倍(161.4人 vs. 5.2人/100万人)
- 腸管出血性大腸菌(STEC)の発生率
- EUは日本の約10倍(21.3人 vs. 2.1人/100万人)
- リステリア症の発生率
- EUでは100万人あたり6.2人、日本はゼロ(※)
- カンピロバクター症の発生率(参考)
- EUは日本の約18倍(308.7人 vs. 16.7人/100万人)
📌 (※)リステリア症に関する注意点
日本の統計ではリステリア症による食中毒事例は確認されていないが、これは「発生していない」からではなく、「検出・報告されていない」事例が多いと考えられる。EUではリステリア菌の全ゲノム解析プロジェクトが進められ、幅広い食品を対象とした厳格な規格が設けられているのに対し、日本の規格対象は生ハムやナチュラルチーズなど、限られた食品にとどまっている。病院ではリステリア感染症の報告があることから、食中毒としての検出率が低いだけの可能性もある。
📌(※)統計データの解釈に関する補足
EUの発生率データは入院例など重症例が中心となっているため、実際の感染者数はさらに多い可能性がある。つまり、ここで示した数値差はあくまで「報告制度に基づく表面的な比較」であり、必ずしも実際のリスク差をそのまま反映しているわけではないことにも留意が必要である。
なぜ日本はEUに比べて特に食中毒発生率が高くないのか?
日本では依然として指標菌を用いた基準やn=1のサンプリング方式が採用されており、EUのような病原菌を直接ターゲットにした食品安全基準とは異なる。
しかし、今回のデータ分析から明らかになったのは、「日本の基準は緩いにもかかわらず、食中毒の発生率はEUより低い」 という事実である。この矛盾とも言える状況を説明するために、日本の食中毒発生率が低い理由について、筆者の視点から、その要因について考察してみる。
1️⃣食文化と調理習慣の影響
日本では寿司や刺身、生卵などの「生食文化」が根付いており、本来であれば微生物リスクが高くなるはずである。しかし、生食を前提とした高度な衛生管理が確立されていることが、食中毒リスクを抑えている大きな要因と考えられる。
- 刺身・寿司の衛生管理: 魚介類は流通の段階で厳格な衛生管理が施され、温度管理が徹底されている。
- 飲食店での衛生管理意識の高さ: HACCP導入は遅れ気味だが、個々の店舗レベルでのマニュアルや従業員教育が行き届いている。

2️⃣食品流通・サプライチェーンの違い
日本とEUでは食品の流通システムが大きく異なる。この違いが、食中毒の発生率にも影響を与えている可能性がある。

- 日本の流通は短く、鮮度管理が徹底
- 地産地消が比較的多く、食品が生産から消費までの時間が短い。
- 温度管理が厳しく、新鮮なうちに消費される。
- コンビニやスーパーの回転率が高く、長期保存せずに食べる傾向がある。
- EUは広域流通でリスクが高まる
- 異なる国で生産された食品がEU各国をまたいで流通する。
- 食品が輸送される過程で汚染リスクが増加する。

このように、日本では食品が流通する時間が短く、適切な温度管理が施されることで、細菌の増殖リスクが抑えられていると考えられる。
3️⃣ルールで縛るEU、現場で守る日本
日本とEUでは、食品安全の管理方法が根本的に異なっている。EUは食品微生物規格の整備を重視し、科学的なアプローチでリスクを管理する。一方、日本は規則の改正スピードが遅いものの、現場レベルでの衛生管理が強く機能し、結果として食中毒の発生率が低い。
✅ 日本のアプローチ:「現場での運用と道徳観」
- 規則の改定スピードは遅いが、現場の職人気質や道徳観によって自主的に管理が徹底される。
- HACCP導入も遅れたが、企業独自の衛生基準や従業員教育が強く機能している。
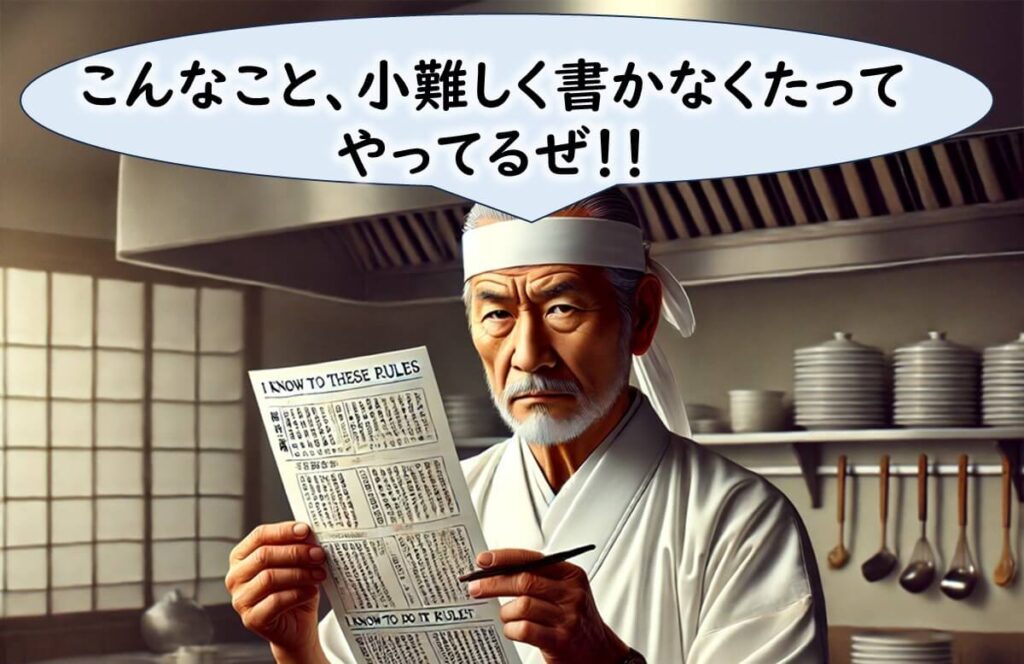
✅ EUのアプローチ:「規則でリスクを管理する」
EUでは、加盟国が共同で科学的議論を重ね、迅速に統一された食品安全規則を策定する体制が整っている。こうした制度の整備は日本よりはるかにスピーディで合理的だといえる。

しかし一方で、科学的理想が先行し、現場の実情が十分に制度に反映されないという構造的なギャップもある。
EUの専門家会合では、各国代表が建設的な議論を重ねるが、実際には「自国の事情をここで正直に話すのは難しい…」と感じる担当者も少なくない。
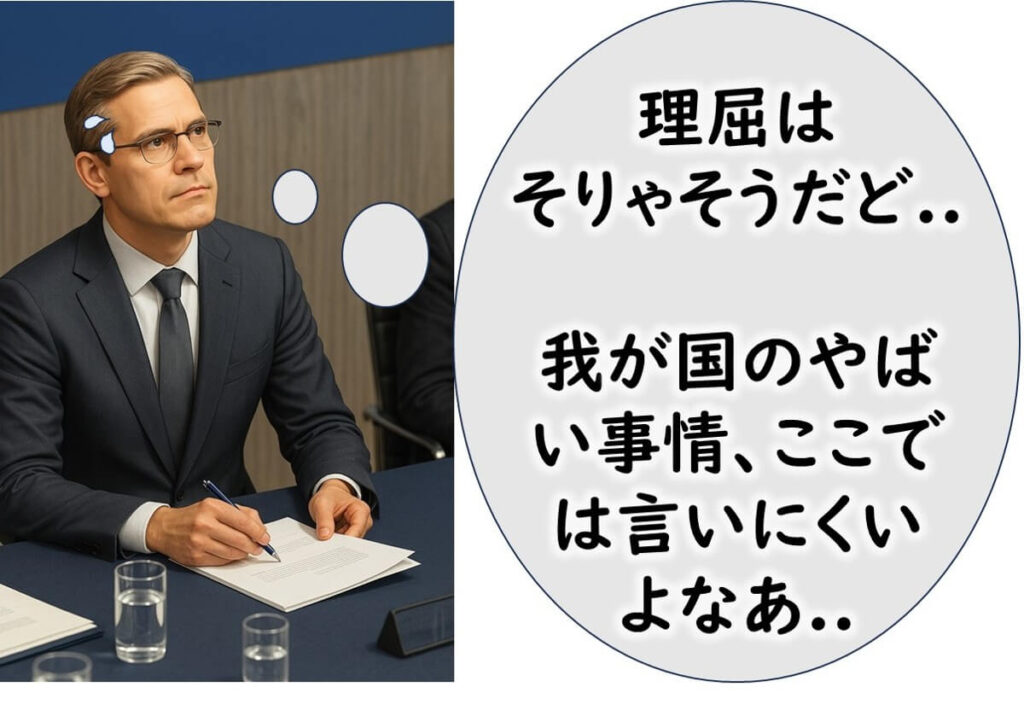
つまり、制度が理想的に設計されていても、それが各国の現場で十分に実行されるとは限らない。
EUでは、制度設計が中央集権的に進むため、各国の実情や流通現場の事情が十分に反映されにくく、現場とのギャップが生じることもある。
このため、「制度は先行するが、現場の運用は追いつかない」という構造が、結果として統計上のリスクの高さに影響している可能性もある。

改めて、日本の食品微生物規格はこのままでよいのか?
今回のデータ分析から、日本の微生物規格は国際基準と比べて緩いにもかかわらず、食中毒の発生率は低いという事実が見えてきた。これは、日本の流通の速さ、衛生意識の高さ、現場レベルでの柔軟な管理がリスクを抑えているからこそ成り立っているとも言える。
しかし、日本の食品業界が国際市場で戦っていくためには、EUや米国のリスクベース基準との整合性も求められる。統計的な精度と現場の実態、国内の運用のしやすさと国際整合性――このバランスをどう取るべきか。
たしかに、日本国内だけを見れば、指標菌を含む昭和型の規格でも「結果が良いから現状維持でよい」という空気は根強い。しかし実際には、輸出入の現場ではそうもいかない。とくにEU諸国との取引では、基準の不整合が摩擦の原因になっており、企業の担当者からも「この規格のままでは説明が通じない」といった声がしばしば聞かれる。

これは単純な「規格を厳しくすればよい」という話ではないが、制度の国際的な互換性をどう確保するかという意味で、解かねばならない課題である。


