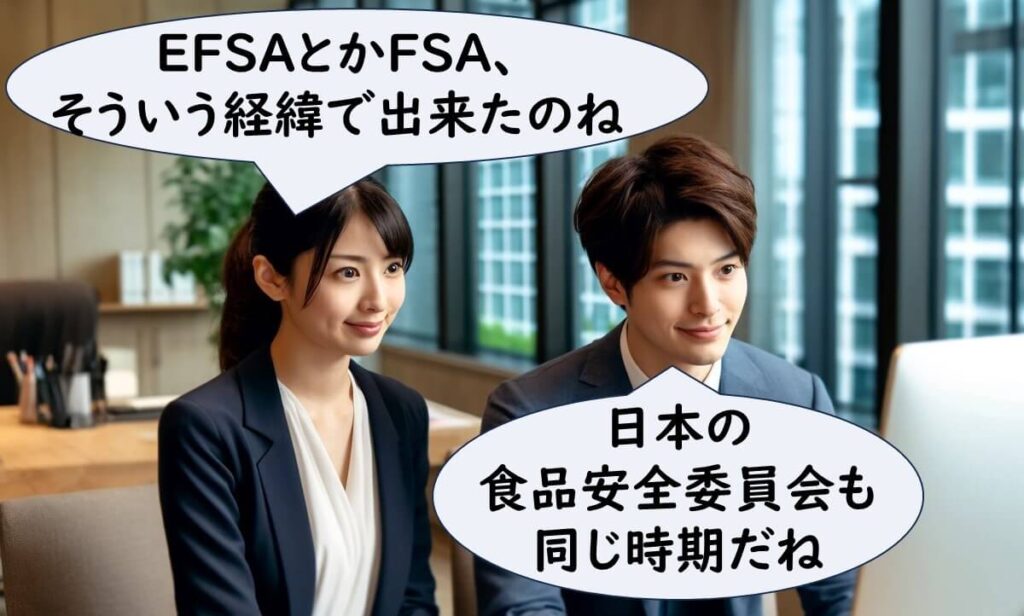1990年代にイギリスで発生したBSE危機は、世界中の食品安全政策に革命をもたらした。この記事は、その教訓から生まれたイギリスの食品基準庁(FSA)、ヨーロッパの食品安全機関(EFSA)、そして日本の食品安全委員会の設立背景に迫り、これらの機関がどのようにして食品のリスク評価と管理の新しい標準を設けたかを解説する。
英国から世界を震撼させたBSE(牛海綿状脳症)問題
1990年代にイギリスで発生したBSE(牛海綿状脳症)問題は、その後の食品安全政策に大きな変化をもたらした。
BSE問題とは?
狂牛病
BSEはイギリスで初めて正式に診断された。感染の原因は、感染した動物の肉骨粉を牛の飼料として再利用したことによるものだった。BSEはプリオンと呼ばれる異常なタンパク質が脳に蓄積し、脳組織が徐々に破壊されることで起こる疾患である。牛におけるBSEの症状は、穏やかだった牛が異常に恐怖を感じるようになり、ふらつきコントロールの効かない動き、食欲不振、体重減少、震え、重度の運動障害へと徐々に進行し、最終的には致命的になる。1980年代後半、イギリスでの症例が急増し、この問題が農業と公衆衛生の重大な危機となった。
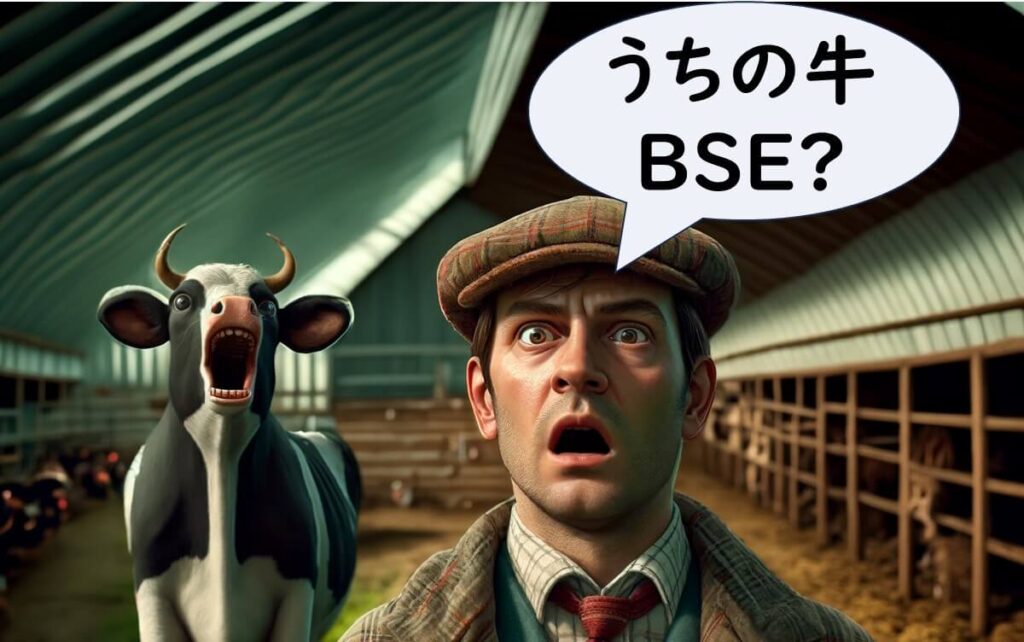
人にも感染
1996年、イギリス政府はBSEと新型クロイツフェルト・ヤコブ病(variant Creutzfeldt‐Jakob disease, vCJD)との関連があることを公式に認めた(Will et al.1996)。vCJDは、BSEに感染した牛肉を食べた人間に発症する致命的な病気である。初期段階では、記憶障害、うつ状態、行動の変化が見られ、次第に調整運動障害が現れ、歩行が困難になる。症状は進行し、認知症、筋肉のけいれん、最終的には言語や運動機能が失われる。多くの場合、診断から数年で死に至る。
1990年代後半、世界中がBSE問題でパニックとなり、多くの国がイギリス産牛肉の輸入を禁止した。EU全体で牛の肉骨粉の飼料使用が禁止された。

リスク管理機関としての英国農業省への批判
BSE危機がイギリス国内、EU、そして世界でどれほど深刻であったかを示すのが、リスク評価機関の誕生である。
1980年代末から1990年代にかけて、イギリスで発生したBSE(牛海綿状脳症)の危機に対する対応は、主に農業省(Ministry of Agriculture, Fisheries and Food、MAFF)が中心となって行われた。この時期、MAFFはイギリスの食品安全政策に関するリスク評価とリスク管理の両方を担当しており、これが後の問題の一因とされた。
MAFFは、農業政策と食品安全の両方を担当していたため、農業の促進と公衆衛生の保護という二つの場合によっては対立する目的を同時に追求する必要があった。BSE問題が明るみに出た際、MAFFは以下のような活動を行っていた(BSE inquiry)。
- リスク評価: BSEの発生とその人間への影響(特に変異型クロイツフェルト・ヤコブ病、vCJD)に関する科学的データを収集し評価。
- リスク管理: BSEの拡散を防ぐための政策と措置を策定し実施。これには、感染牛の殺処分、肉骨粉の飼料への使用禁止、特定危険部位の除去どが含まれた。
MAFFによるリスク評価とリスク管理の統合は、政策決定プロセスにおける透明性と信頼性の欠如を招いた。政府がBSEのリスクを過小評価しているとの批判が高まり、結果的に公衆の不信感を招くこととなった。また、農業の利益を代表する立場から、問題を軽減するためにリスクを過小評価しているとの見方もあった。
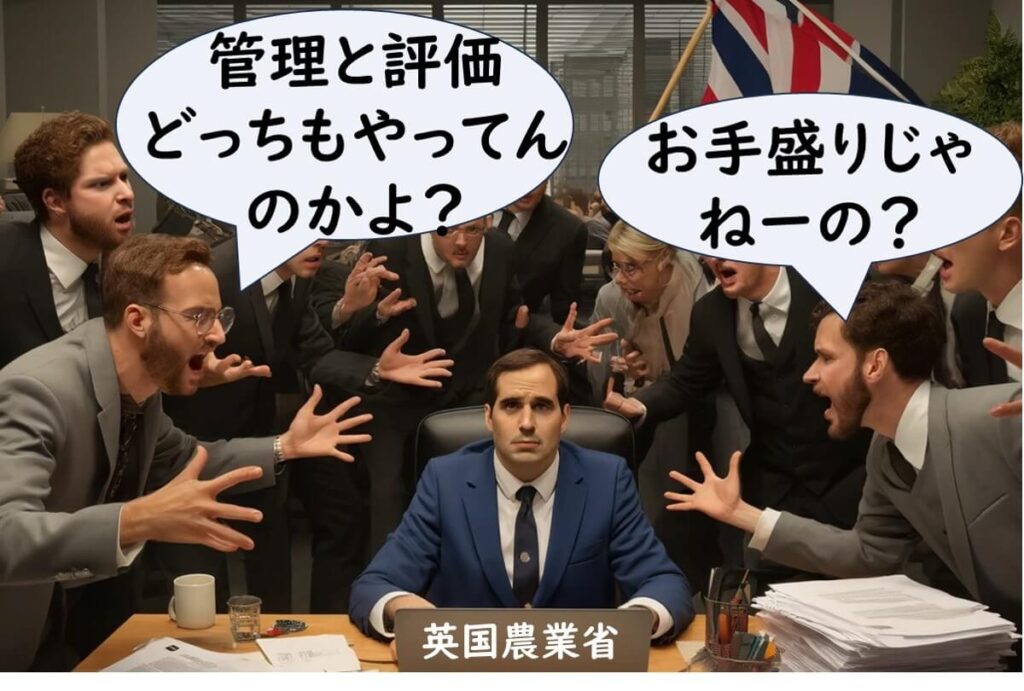
英国で食品基準庁の設立(2000)
上記のような国民からの批判を受ける形で、2000年、英国政府は食品基準庁(Food Standards Agency, FSA)を設立し、農務省から食品安全管理の機能を移管した。FSAは、食品のリスク評価と一部のリスク管理を担うこととなり、その主な目的は、食品安全に関する政策と実践の透明性を確保することだった。

ただし、FSAの設立は後にEUで設立されるEFSAと異なり、リスク管理の機能も一部担っており、完全にリスク評価に特化したわけではなかったが、リスク評価を前面に出した新しいアプローチは画期的だった。
EUでEFSAが設立(2002)
BSE危機を受けて、特に欧州連合(EU)は食品安全管理システムを根本から見直した。この過程で、リスク評価を行う独立した科学的機関としての欧州食品安全機関(European Food Safety Authority, EFSA)が2002年に設立されることになり、リスク評価とリスク管理の明確な分離が図られた。EFSAの設立は、リスク評価の透明性と科学的客観性を高めるという国際的な議論の末に誕生したものである。EFSAはイタリアのパルマ市に本拠地を置いており、ここに本部が設置されている。
EFSAの主な役割は、EU加盟国全体の食品安全に関連するリスク評価を独立して行うことであり、リスク管理は各国政府や他のEU機関が担当することとされた。EFSAが設立される前も、ヨーロッパには各国ごとに食品安全に関する規制や機関が存在していた。しかし、EUレベルで食品安全に対する統一されたアプローチや中央集権的なリスク評価機関は存在せず、国によって対応が異なっていた。

EU全体をカバーし、また、純粋に科学的なエビデンスに基づくリスク評価に特化したEFSAの誕生により、リスク評価の独立性が強化され、EU全体での食品安全規制の均一性が保たれることとなった。
日本で食品安全委員会の設立(2003)
日本でも、当時、BSEの問題が吹き荒れたのは例外ではない。食品安全に対する体制強化が求められ、2003年に内閣府に食品安全委員会が設立された。この機関は厚生労働省や農林水産省とは独立しており、食品のリスク評価を専門に行う。食品安全委員会の設立は、リスク評価の透明性を高めるとともに、国内外の食品安全基準に対する一貫性を確保するためのステップだった。この委員会は、科学的な根拠に基づいた食品の安全評価を行い、その情報を政府に提供して政策決定のサポートを行っている。さらに、食品に関するリスク情報の公開を通じて、消費者の理解を深める役割も果たしている。

日本の食品安全委員会はEFSAと情報共有や意見交換を通じて、連携して食品安全の確保に取り組んでいる。
まとめ:食品安全管理の国際的な進化
BSE危機が引き起こした食品安全への警鐘は、世界各国における食品安全管理の改革を促した。イギリスのFSA、ヨーロッパのEFSA、そして日本の食品安全委員会の設立は、リスク評価とリスク管理の明確な分離を通じて、食品安全に対する透明性と科学的根拠の重要性を高める画期的なステップだった。これらの機関はそれぞれ異なる文脈で設立されたが、共通する目的は公衆の健康を保護し、食品産業における信頼を再構築することにある。
本ブログではEFSAの評価書やFSAのガイドラインをよく紹介するが、食品微生物の入門者がこれらの組織の成立経緯や位置づけを理解できるようになることが、本記事の目的である。