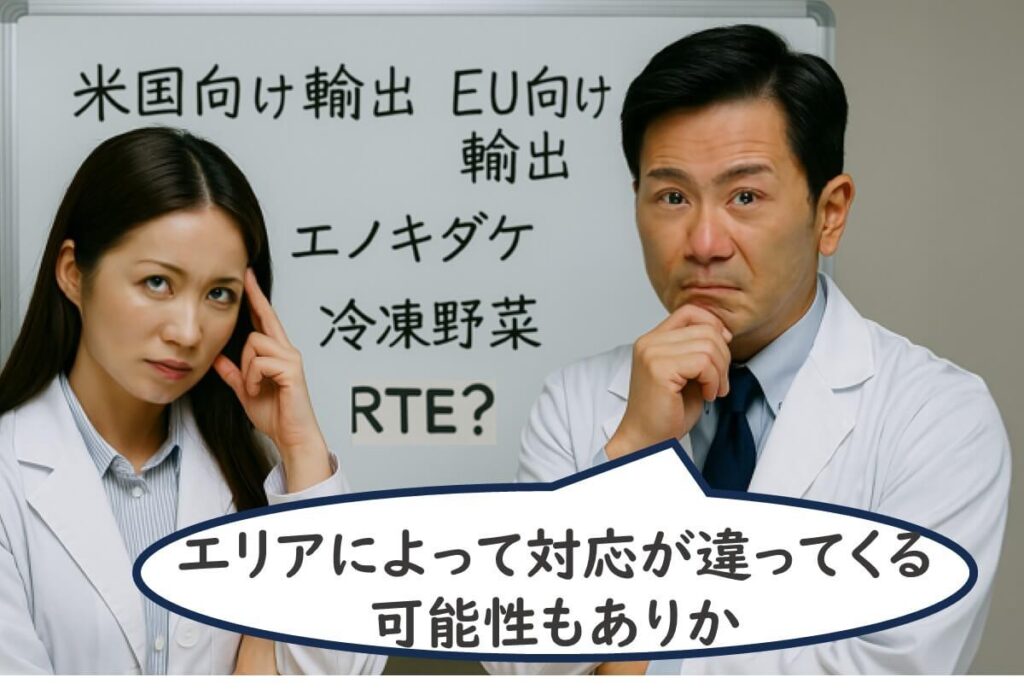米国では、韓国・中国産エノキダケ由来のリステリア食中毒(2020年/2022–23年)以降、州やFDAの検査により毎年のようにリコールが発生している。エノキダケは、日本や韓国、中国では加熱調理を前提とするのが一般的である。だからこそ、輸入されたエノキダケが米国でリステリア陽性を理由に即座にリコールされると、多くの人々は「なぜ?」と強い疑問を抱く。
本記事では、この背景にある米国の“実態ベース”の制度設計と、EUの“製造者の意図ベース”の制度設計を対比しながら解説する。こうした考え方の違いを理解することは、日本の食品企業にとって国際的な規制動向を見据える上で重要な参考となるだろう。
関連記事:エノキダケとリステリア食中毒
米国のアプローチ ― 実態ベースのRTE解釈
米国FDAの方針文書(CPG 555.320)は、RTE(Ready-to-Eat)食品を「消費者が慣習的に加熱せず食べる、あるいは加熱しなくても食べられそうに見える食品」と定義している。つまり、ラベルに「加熱して食べること」と書かれていても、実態として生や半生で利用されていればRTEと見なされる。
引用:FDA Compliance Policy Guide (CPG 555.320)
"Ready-to-eat food" (RTE food) means a food that is customarily consumed without cooking by the consumer, or that reasonably appears to be suitable for consumption without cooking by the consumer.A food may be considered to be suitable for consumption without cooking by the consumer, and thus a RTE food, even though cooking instructions are provided on the label. For examples, fresh and frozen crabmeat and individually quick frozen (IQF) peas and corn may be RTE foods. Some consumers eat such products without cooking, because they appear to be ready-to-eat.
訳: RTE(Ready-to-Eat)食品とは、「消費者が慣習的に加熱せず食べる食品、または加熱しなくても食べられるように見える食品」を意味する。ラベルに加熱指示が書かれていても、実際に消費者が加熱せずに食べている場合はRTE食品と見なされる。例えば、蟹肉や冷凍野菜(グリーンピースやコーンなど)はRTE食品として扱われることがある。

実際、米国ではサラダに生でトッピングされたり、調理済みのスープに追い入れられたりすることがあり、過去にはリステリアによるアウトブレイクも報告された。疫学的に「生や半生で食べられている」ことが確認された時点で、米国の目にはRTEリスク食品として映る。
このため、FDAは韓国・中国産のエノキダケを2020年の集団発生を契機として輸入警告(Import Alert 25-21:リステリア・モノサイトゲネス検出による各種食品の差止め)に追加し、リステリア陽性が出れば即座に拘留・リコールに踏み切る仕組みを整えた。
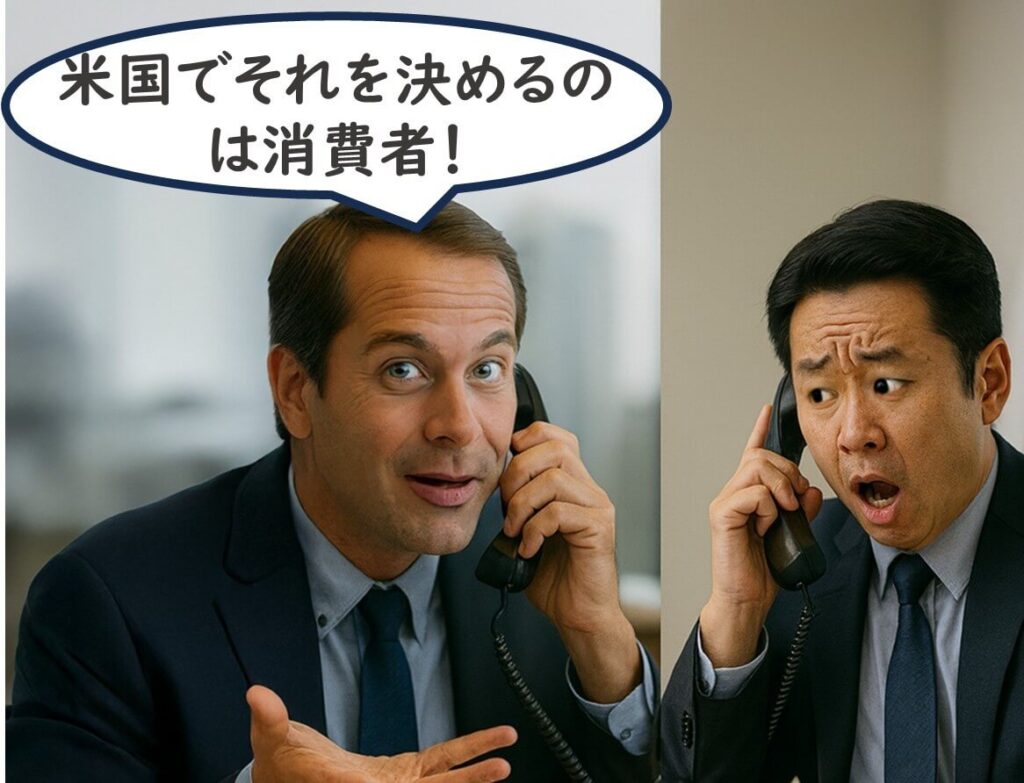
EUのアプローチ ― 製造者の意図に基づくRTE定義
一方でEUの規則(EC 2073/2005)は、「製造者が加熱不要として意図する食品=RTE」と定義している。つまり冷凍野菜やエノキダケのような「加熱前提」の食品は、通常は非RTE扱いであり、リステリアに対する厳格な規格の対象外とされる。
引用:EC 2073/2005
‘ready-to-eat food’ means food intended by the producer or the manufacturer for direct human consumption without the need for cooking or other processing effective to eliminate or reduce to an acceptable level micro-organisms of concern;
— Regulation (EC) No 2073/2005, Article 2(g)訳:RTE(Ready-to-Eat)食品」とは、製造者または製造業者が、加熱またはその他の処理を行うことなく、直接人が消費することを意図する食品をいう。ただし、その処理は、問題となる微生物を許容できる水準まで排除または低減するのに有効である場合を除く。
2015~2018年には、ハンガリー工場の冷凍スイートコーンが原因となり、EU域内で多国間にわたる大規模なアウトブレイクが発生した。このときEU当局は、製品回収や消費者への「冷凍野菜は必ず加熱すること」という注意喚起を行ったが、冷凍野菜をRTEとして扱うような制度改正には踏み込まなかった。

EUの立場は依然として「製造者が加熱を前提として製造、出荷した食品は非RTE」であり、ただしリスクが顕在化すれば一般食品法に基づいて市場から排除する、という対応を取っている。近年では、リステリア規格全般について段階的な見直し作業が進められているが、現時点でも「冷凍野菜=非RTE」という基本的な扱いは維持されている。
比較から見える制度設計の差
同じ「加熱前提の野菜」であっても、両者の制度設計には大きな違いがある。
- 米国
- 消費者の実態ベースでRTEかどうかを判断。
- 生食・半生利用の可能性があればRTEと見なし、リステリア検出=即リコール。
- EU
- 製造者の意図を基準にRTEか非RTEを判断。
- 冷凍野菜は非RTEとして扱い、リステリア規格の対象外。
- ただしアウトブレイクが起きれば一般食品法で回収・注意喚起。
この差があるため、米国では「生で食べられる可能性がある」と認定されれば即リコールにつながり、EUでは同じ事態が起きても「非RTE扱いを前提に一般法で対応する」方向になる。
結論
日本や韓国、中国の感覚では「エノキダケは加熱用であってRTEでないのだからリコールは不思議」と思えるかもしれない。しかし米国では、実際にどう食べられているかに基づいて食品を評価するため、リステリア陽性が出れば即リコールとなる。一方EUは、あくまで製造者の意図を重視し、非RTE食品は規格対象外とする。ただし現実に被害が出れば、一般法で回収や注意喚起を行う。
この違いは、同じ冷凍野菜でも「米国なら即リコール、EUでは制度上は非RTEのまま対応」という形で現れる。エノキダケは、まさに制度設計の思想の差を示す好例である。
👉 要するに、米国は“消費者の実態重視”、EUは“製造者の意図重視”。
この一点を押さえると、両者の対応の違いがすっきり理解できるだろう。